法定12項目講習の内容の注意点
今回は、法定12項目研修の内容の注意点についてのお話です。
何を書くかというと、法定12項目の研修内容は、国土交通省のマニュアルにある内容をやらないと「指導不足」になるということです。
法定12項目は、その名の通り12項目あります。
どうやって実施するかは国土交通省告示1366号に記載されています。
やり方について記載がある部分を抜粋すると
3.指導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項
(1)運転者に対する指導及び監督の意義についての理解
(2)計画的な指導及び監督の実施
貨物運送事業者は、運転者の指導及び監督を継続的、計画的に実施するための基本的な計画を作成し、計画的かつ体系的に指導及び監督を実施することが必要である。
(3)運転者の理解を深める指導及び監督の実施
(4)参加・体験・実践型の指導及び監督の手法の活用
(5)社会的情勢等に応じた指導及び監督の内容の見直し
(6)指導者の育成及び資質の向上
(7)外部の専門的機関の活用
こんな感じです。
そして別紙に12項目が書かれているのですが、この内容を基にして、国土交通省で「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」(以下、実施マニュアル)を作成しています。
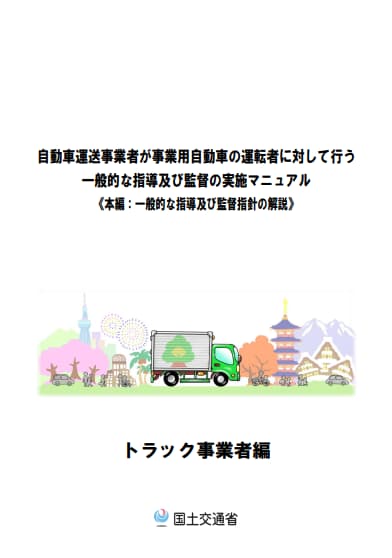
これは、学校教育で言うところの文部科学省の作成する「学習指導要領」にあたると思います。
それでこの実施マニュアルを基にしていくつかの機関によって、独自のマニュアルが作られています。
法定12項目を国土交通省が求める内容をしっかりやると、結構な時間がかかるということで短縮を考えるケースがあります。
法定12項目一部省略は指導不足になる
ここで注意が必要です、法定12項目講習の内容は、実施マニュアルにある内容をちゃんとやらないと「指導不足」になります。
トレーラーの部分とか危険物のところとかは、自分の会社では、扱わないということであれば、一部省略ができます。危険物に関しては少量取り扱いということで資格なしで運ぶことができるケースもありますので、まったくやらない訳にはいきませんが、それでもガッチリやる必要はありません。
しかしトレーラーや危険物の課題以外のところを省くと「指導不足」になります。
一般貨物運送事業社内教育アカデミー(ISA)を始めてから、同じように法定12項目に関する教育を提供しているところをみると、案外してはいけない省略をしているケースがみられます。注意が必要です。
動画教材も多く出回っていますが、動画で講習をする場合も、グッドラーニングさんのように、しっかり作りこんだ教材を使用することが大切です。
基本は実施マニュアルの内容全部をやることです
実施マニュアルは、学習指導要領と同じですので、その内容が満たされているのであれば、工夫した解説にしたりオリジナルな内容を加えたりすることができます。
実施マニュアルの内容は結構ガッチリなので、そのまんま講習をしても、まあまあ時間がかかります。
年間とおして毎月1回で12回として、早口で解説して1講習15分は欲しいところです。15分では充分な理解をしてもらうことはできませんが「やったこと」にはなります。
そして、絶対×なのが、一部だけで済ませてしまうこと。
法定12項目のⅢが長くなるので、半分くらいまでやって残りは来年
これ×です。
もし何か問題があって、監査が入り「研修やってますか」ということで内容をチェックされたときは「不十分」の判定になります。
せっかく講習時間をとってやっていますのでもったいないですね。
一般貨物運送事業社内教育アカデミー(ISA)の法定12項目研修は、実施マニュアルの内容をそのまま行います。
講習時間をどのくらいとることができるかによって、研修のやり方を工夫しなければなりません。どんなに短い時間であっても、実施マニュアルの内容を網羅することが必須です。
それで、国土交通省の作成した実施マニュアルの内容をそのまま動画にしたら、でAIアバターにAI音声「ちょっと早口」で行うとどんな感じになるかですが、一般貨物運送社内教育アカデミー(ISA)のホームページで観ることができますので確認してみてください。
ここではYouTubeを使っていますので、YouTubeチャンネルで観ることもできます。
7月4日17時現在まだ法定12項目Ⅳまでしかできていませんが、これから少しずつⅫまでアップロードしていきます。
まとめ
内容の省略は「研修が不十分」の判定になることがあります。
法定12項目研修の内容の注意点「基本は実施マニュアルの内容を全部やること」です。
「この項目は半分くらいまでやって残りは来年」は×ですので絶対にやめましょう

法定12項目


